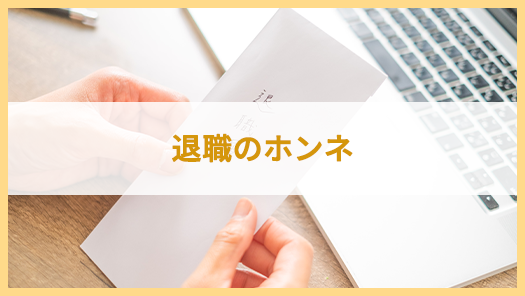離職率が高いことで企業が直面する3つのリスク
高い離職率は、企業経営にさまざまな悪影響を及ぼします。
まずは離職率が高いことで企業が直面する具体的なリスクを理解し、対策の必要性を認識しましょう。
リスク(1)採用・育成コストの損失
採用から育成までにかけたコストが離職により回収できず、企業の大きな損失となります。
そもそも採用活動には多額の費用がかかります。
- 求人広告費:求人サイトへの掲載料や採用イベントへの出展費用
- 人材紹介手数料:採用成功時に人材紹介会社へ支払う成果報酬
- 採用担当者の人件費:応募者対応などにかかる人事部門の人件費
- 面接官の時間コスト:現場社員や管理職が面接に割く時間と機会損失
- 研修・育成費用:新入社員研修、OJT、外部研修などの教育投資
これらを合計すると、採用から育成まで数百万円単位でかかるケースは珍しくありません。入社3年以内に離職した場合、これらのコストが完全に損失となり、さらに代替人材の採用コストも発生します。
特に若手社員の早期離職は、育成投資の回収前の退職となるため、企業にとって大きな経済的損失です。離職率が高い企業ほど、採用・育成コストが経営を圧迫し、事業成長の阻害要因となるでしょう。
※関連記事: 採用コスト削減の完全ガイド|コスト上昇の要因と対策を徹底解説
リスク(2)既存社員の負担増加とモチベーション低下
離職者が出ると、その業務を既存社員で分担することになり、一人当たりの業務量が増加します。
業務負担の増加は残業時間の増加、休暇取得の減少や休日出勤などに直結し、残っているメンバーのワークライフバランスが崩れてしまう恐れがあるでしょう。
さらには「なぜ自分だけが残って苦労するのか」という不公平感や、「この会社に将来はあるのか」という不安も広がります。結果として既存社員のモチベーションが低下し、さらなる離職を招く悪循環(離職の連鎖)に陥りかねないといえます。
リスク(3)企業ブランド価値の低下
離職率の高さは求職者や取引先からの信頼を失い、採用難と事業機会の損失につながります。
例えば、転職サイトや新卒者向け口コミサイトで離職率の高さが公開されると、求職者から「ブラック企業では」と敬遠されるリスクが高まります。優秀な人材ほど企業選びに慎重なため、離職率の高い企業は採用競争力が低下し、さらに人材確保が難しくなるでしょう。
また、取引先や顧客からも「安定していない会社」、「長期的な関係が築けない」と判断され、ビジネスチャンスを逃す可能性も考えられます。企業ブランド価値の低下は、採用難と事業機会の損失という二重のダメージにつながる恐れがあるため対策が必要です。
「本当の退職理由」を把握することが離職率低下の第一歩
離職率を低下させるためには、まず離職の真因を正確に把握することが不可欠です。表面的な理由ではなく、本当の退職理由を知るための具体的な方法を解説します。
在職者アンケートで潜在的な不満を可視化する
従業員が退職してしまってからでは、対応は遅いと言わざるを得ません。まずは離職者を出さないためにも従業員満足度(ES)のアンケートを実施し、不満の芽を早期に発見することが大切です。
具体的には以下のように多面的に質問項目を設定し、退職に至る前の潜在的な不満を早期発見しましょう。
- 仕事のやりがい
- 人間関係
- 評価制度
- 労働環境
- キャリア展望
アンケートを実施する際は、匿名性を確保し、正直な回答を得られる環境を整えてください。また、回答率を高めるため、簡潔で答えやすい設問にすると効果的です。
アンケート結果は部署別・年代別に分析し、特定の部署や層で不満が高い場合は、優先的に対策を講じましょう。
エンゲージメント調査で組織課題を特定する
退職につながる要因を特定するためには「従業員エンゲージメント調査」が有効です。調査を通し、組織全体の課題を可視化、改善のサイクルを回しましょう。
エンゲージメント調査とは、従業員が会社に対してどれだけ愛着や貢献意欲を持っているか(エンゲージメントスコアの尺度)を測る調査です。「会社のビジョンに共感しているか」、「上司を信頼しているか」、「成長機会があるか」など、エンゲージメントに影響する要素を多角的に測定します。
このエンゲージメントスコアが低い従業員は離職リスクが高い可能性があるため、早期にフォローすることで離職を未然に防ぐことができるのです。調査結果をもとに、まずは組織全体の課題(マネジメントの質、評価制度の不透明さなど)を特定し、改善策の策定から実施しましょう。
退職面談で本音を引き出す質問をする
退職が決定した従業員に対する面談で「退職した本当の理由」を聞き出すことも求められます。退職面談では「一身上の都合」「キャリアアップ」など建前の理由が語られることが多いため、本音を引き出す工夫が必要です。
「何があれば残ろうと思えましたか?」、「入社時と比べて、何が一番変わりましたか?」など、具体的で答えやすい質問をしましょう。本音を引き出す質問設計と雰囲気づくりが重要です。
場合によっては人事担当者ではなく、第三者(外部サービス)が面談することで、より率直な意見を得られるケースもあります。その上で、退職理由を定量的に集計・分析し、離職の真因(人間関係、評価制度、労働環境など)を特定につなげましょう。
離職率を低下させるための7つの施策
退職理由の真因を明らかにすることができたら、改善に向けた戦略設計と実行に移ります。
ここでは、離職率を低下させるために特に有効な施策を「採用・定着」、「制度・環境」、「マネジメント・健康」の観点から全7つ紹介します。
「採用・定着」フェーズで離職を防ぐ
採用ミスマッチを未然に防ぎ、入社前後のギャップを埋め、早期離職を防止することが重要です。採用段階での適切な情報提供、入社後の体系的な育成プログラムにより、新入社員の定着率を高めましょう。
【入社前】採用ミスマッチ防止
採用時に企業のリアルな情報を提供し、入社後のギャップを減らすことで早期離職を防ぎましょう。
採用活動で企業の良い面だけを伝えると、入社後に「思っていたのと違う」というギャップが生じ、早期離職につながります。RJP(Realistic Job Preview:現実的な仕事情報の事前提示)を実施し、仕事の大変な面や職場の実態も正直に伝えることが大切です。
また、社員との座談会や職場見学を実施し、求職者が実際の働き方や社風を体感できる機会を設けましょう。採用ミスマッチを防ぐことで、入社後の定着率が向上し、無駄な採用コストの削減につながります。
※関連記事: RJP理論とは?4つの効果や具体的な実践方法、導入するメリットを解説
※関連記事: 採用ミスマッチが起きてしまう理由とは?弊害や対策について解説!
【入社後】オンボーディングプログラムの強化
入社後の育成プログラムを体系化し、早期に職場に馴染める仕組みを作りましょう。
オンボーディングとは、新入社員が組織に適応し、早期に戦力化するための育成プログラムです。入社初日から3か月、6か月、1年といった節目で、必要な研修、面談、フォローを計画的に実施しましょう。
また、メンター制度やバディ制度を導入し、困ったときに相談できる先輩社員を配置することで、孤立を防げます。オンボーディングが充実している企業は、新入社員の定着率が高いことから、早期戦力化も実現できるでしょう。
※関連記事: オンボーディングの支援施策や実施するメリット・成功させるためのポイントを解説!
「制度・環境」を整備し離職を防ぐ
公正な評価制度や柔軟な働き方など、従業員が安心して長く働ける制度・環境の整備が定着率向上の鍵となります。
また、離職率低下を単なるコスト削減ではなく、企業価値向上のための人的資本投資として位置づけることが重要です。
評価制度の透明性向上とキャリアパス明示
公正で透明性の高い評価制度を構築し、従業員が将来のキャリアをイメージできるようにしましょう。
「評価基準が不明瞭」、「頑張っても評価されない」という不満は、離職の主要な原因の一つです。評価基準を明文化し、全従業員に公開することで、何をすれば評価されるのかを明確にしましょう。
定期的な1on1面談でフィードバックを行い、評価の根拠を丁寧に説明することで納得感を高めることも大切です。キャリアパスを明示し、「この会社でどのように成長できるか」を具体的に示すことで、長期的なモチベーションを維持につながります。
働き方の柔軟性を高める
リモートワークやフレックスタイム制度など、多様な働き方を選択できる環境を整えましょう。昨今はワークライフバランスを重視する従業員が増えており、働き方の柔軟性は定着率に直結する重要な要素です。
リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務など、ライフステージに応じた働き方を選択できる制度を導入しましょう。また、育児や介護との両立がしやすい環境を整えることで、優秀な人材の流出を防げます。
柔軟な働き方を実現している企業は、採用競争力も高まり、優秀な人材を引きつけられるでしょう。
「人的資本経営」の推進
離職率低下を単なるコスト削減ではなく、人的資本への投資として経営戦略に位置づけましょう。
人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上を目指す経営手法です。離職率の低下は、採用・育成コストの削減だけでなく、組織の知識・ノウハウの蓄積、従業員エンゲージメントの向上、企業文化の醸成など、長期的な競争優位性の構築につながります。
具体的には、人材育成への積極投資、スキル開発支援、キャリア自律の促進など、従業員の成長を支援する仕組みを整備しましょう。離職率や従業員満足度などの指標を可視化し、PDCAサイクルを回しながら人材の定着・育成を経営戦略の中核に据えることで、持続的な企業価値向上を実現できます。
「マネジメント・健康」の観点から離職を防ぐ
管理職のマネジメント力向上と従業員の健康支援は、離職防止の基盤となります。
上司との良好な関係構築と心身の健康維持により、従業員が安心して働ける職場環境を実現しましょう。
マネジメント層のコミュニケーション力強化
管理職の1on1スキルやフィードバック力を向上させ、部下との信頼関係を構築しましょう。
「上司との関係」は離職理由の上位にランクインする重要な要因です。管理職向けにコミュニケーション研修や1on1研修を実施し、部下の話を聴くスキル、適切なフィードバックのスキルを習得させましょう。
また、定期的な1on1ミーティングを制度化し、部下の悩みや不満を早期にキャッチできる体制を作ることが大切です。マネジメント層のコミュニケーション力が向上することで、部下のエンゲージメントが高まり、離職率は低下すると考えられます。
メンタルケア・健康支援の強化
従業員のメンタルヘルスケアと健康支援を充実させ、心身の不調による離職を防ぎましょう。
メンタルヘルス不調は離職の大きな要因の一つです。ストレスチェックの実施、産業医面談の機会提供、外部カウンセリングサービスの導入など、従業員が気軽に相談できる環境を整えることが重要です。
また、管理職向けにメンタルヘルス研修を実施し、部下の不調サインに早期に気づけるスキルを身につけてもらいましょう。定期的な健康診断の実施や、健康増進プログラムの提供なども効果的です。従業員の心身の健康を守ることで、安心して長く働ける職場環境が自然と構築されやすくなるのです。
離職率低下に向けた施策の優先順位の決め方
すべての施策を同時に実行するのは現実的ではありません。限られたリソースで最大の効果を得るために、施策の優先順位を適切につける方法を解説します。
離職理由のうち上位3つから着手する
退職面談やアンケートで明らかになった離職理由の上位から優先的に対策しましょう。
すべての施策を同時に実行するのは現実的ではないため、自社の離職理由トップ3に絞って対策を講じると効果的です。たとえば、離職理由の1位が「評価制度への不満」なら、評価制度の見直しを最優先で実施しましょう。
離職理由が明確でない場合は、まず退職面談やアンケートで真因を把握することから始めてください。課題が明確になることで、経営層への説明もしやすくなり、予算や人員の確保がスムーズになります。
即効性と投資対効果のバランスを見る
短期間で効果が出る施策と、中長期的に効果が出る施策をバランスよく組み合わせましょう。離職率低下には時間がかかるため、短期的な成果を示しながら、中長期的な施策も並行して進めることが重要です。
短期施策としては、1on1ミーティングの導入、退職面談の強化など、比較的低コストの施策が多く、中長期施策には、評価制度の再構築、オンボーディングプログラムの体系化など、時間と投資が必要なもの挙げられます。
| 時間軸 | 主な施策 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短期施策 | ・1on1ミーティングの導入 ・退職面談の強化 ・相談窓口の設置 |
比較的低コストで実施でき、早期に効果を実感しやすい |
| 中長期施策 | ・評価制度の再構築 ・オンボーディングプログラムの体系化 | 時間と投資が必要だが、根本的な組織改善につながる |
短期で成果を出すことで、経営層や現場の信頼を得られ、中長期施策への投資を引き出しやすくなるでしょう。
経営層の理解と予算を確保できるものから始める
経営層が重要性を理解していて、予算を確保できる施策から着手することで、実行可能性を高めましょう。
どれだけ良い施策でも、経営層の理解と予算がなければ実行できないため、まず経営層を説得できる材料を揃えることが大切です。離職率の高さがもたらす経済的損失(採用・育成コストの損失、生産性の低下など)を数値で示し、対策の必要性を訴えましょう。
特にROI(投資対効果)を明確に示せる施策から着手し成功事例を積み重ねることで、次の施策への投資を引き出せます。経営層を巻き込むことで、全社的な取り組みとして推進でき、施策の実効性が高まるでしょう。
短期的な成果と長期定着を見据える
目先の離職率改善だけでなく、組織文化の定着まで見据えた施策設計が重要です。短期的な施策で一時的に離職率が下がっても、根本的な組織文化や仕組みが変わらなければ、再び離職率が上昇してしまいます。
1on1ミーティングの導入など即効性のある施策で成果を示しつつ、評価制度の改革やマネジメント力強化など、組織文化を根本から変える施策にも並行して取り組みましょう。
さらに、短期施策で得られた成果や課題を中長期施策にフィードバックし継続的に改善していくPDCAサイクルを確立することが、持続的な離職率低下につながります。全社的な意識改革を伴う取り組みとして位置づけることで、一過性の対策で終わらない定着を実現できます。
離職率低下の成果を可視化するKPIと改善サイクル
施策を実行したら、その効果を適切に測定し、継続的に改善していくことが重要です。離職率低下の成果を可視化するためのKPIと改善サイクルの回し方を解説します。
離職率以外に追うべき3つの指標
離職率だけでなく、あわせて以下の3つの指標についても測定しましょう。
- エンゲージメントスコア
- 定着率
- 退職予備軍の割合
離職率は結果指標であり、離職が起きてから気づくものであるため、先行指標として他の指標も一緒に追う必要があります。
エンゲージメントスコアは、従業員の会社への愛着度を測る指標であり、スコアが低い従業員は離職リスクが高いといえます。定着率は、特定期間(入社1年後、3年後など)での在籍率を示し、早期離職の傾向を把握することが可能です。
また、退職予備軍の割合は、アンケートで「転職を考えている」と回答した従業員の割合です。これらの指標をもとに早期に対策を講じることで離職を防げます。
四半期ごとの振り返りとアクション設計
施策は実行したら終わりではなく、定期的に効果を測定し、PDCAサイクルを回すことが重要です。
四半期ごとに、離職率、エンゲージメントスコア、アンケート結果などを確認し、施策の効果を検証しましょう。効果が出ていない施策は、原因を分析して改善するか、リソースの無駄を避けるために中止してください。
効果が出ている施策は、他部署への横展開や、さらなる強化を検討しましょう。データに基づいた意思決定を行うことで、より効果的な施策に集中できます。
成果を定着させるための社内共有と横展開
特定の部署で離職率が低下した施策は、他部署でも効果が期待できるため、積極的に横展開することが大切です。
成功事例を社内報や全社会議で共有し、「こういう取り組みで離職率が下がった」という実績を可視化しましょう。他部署のマネージャーに成功事例を紹介し、自部署でも試してもらうことで、組織全体の改善が加速します。
成功事例を共有することで現場のモチベーション向上にもつながり、組織全体の離職率低下の好循環を生み出すでしょう。
「アルムナイ採用」で離職を損失で終わらせない
離職率低下の施策に加えて、アルムナイ採用を導入することで、実質的に離職による損失を軽減できます。
アルムナイ採用とは、一度退職した従業員を再雇用する制度です。退職者を完全な損失として終わらせるのではなく、「会社のファン」として良好な関係を維持し、再雇用や人材紹介、企業ブランドの発信源として活用する視点が重要です。
退職者とのネットワークを構築することで、即戦力人材の再雇用による採用・育成コストの削減、アルムナイによる採用ブランディングの強化、質の高い人材紹介などのメリットが得られます。
離職を単なる損失として捉えるのではなく、長期的な関係構築の機会と位置づけることで、採用競争力と企業価値の維持・向上につなげられるでしょう。
※関連記事: 【人事部必見】アルムナイ採用のデメリットを知り失敗を回避する方法
離職率を下げるには、まず"本音"を知ることから
離職率を低下させるためには、表面的な対策ではなく、離職の真因を正確に把握したうえでの対策が重要です。まずは本当の退職理由を知るところから始めましょう。
真因が明らかになったら、具体的な施策を、自社の状況に応じて優先順位をつけて実行してください。施策を実行したら、離職率だけでなく、エンゲージメントスコアや定着率などの先行指標も含めて効果を測定します。さらに、四半期ごとにPDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことで、持続的な離職率低下につながるでしょう。
私たちパーソルビジネスプロセスデザインが提供する「退職のホンネ」サービスは、第三者による退職面談を通じて、従業員の本音を引き出し、離職の真因を可視化するサービスです。人事担当者では聞き出せない率直な意見を収集し、データに基づいた離職率低下施策の立案を支援します。
従業員が退職する本当の理由(ホンネ)を知り、効果的な対策を講じたい方は、ぜひ導入をご検討ください。