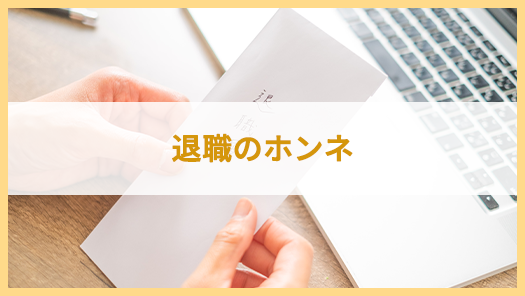退職理由の本音と建前とは
なぜ退職者は本音を語らないのでしょうか。理由を尋ねると「キャリアアップ」「家庭の事情」「給与」など、よくある答えが返ってきます。しかし、これらは建前であることが多いのです。本音と建前のギャップこそ、組織改善を難しくする最大の要因です。
この本音をどう引き出すかが、離職防止とエンゲージメント向上のカギになります。
本音と建前の違い
退職理由には「本音」と「建前」があります。建前は上述のとおり、社会的に受け入れられやすい説明です。一方、本音は「会社の評価制度への不信」「上司との関係悪化」「過重な業務負荷」など、言いづらい要因が多く含まれます。
このギャップが生まれる背景には、社会的な配慮や心理的防衛、そして統計やアンケート調査の限界があります。結果として、企業は「キャリアアップ希望者が多いから研修を強化」といった表面的な対策に終始し、真因である「評価の納得感不足」や「役割設計の不備」を見逃しがちです。
本音を引き出すには、退職者が安心して話せる環境づくりと、具体的な対話が欠かせません。建前の裏にある本質を見極めることが、離職防止と組織改善のカギです。
本音が出にくい理由
退職面談や面接で本音を話すのは、退職者にとって簡単なことではありません。その背景には、いくつかの心理的なハードルがあります。
- 人間関係への配慮 :上司や同僚との関係を悪化させたくない、波風を立てたくないという思いがある
- 評価や再雇用への不安:「率直に話すと悪印象を残すのでは」という懸念が、本音を抑える
- 心理的安全性の欠如:面談担当が社内の人事や上司だと、どうしても話しづらくなる
- 言語化の難しさ:退職理由は複数の要因が絡み合うため、本人も整理しきれていないことがある
さらに、日本特有の「波風を立てない文化」や、質問の仕方、第三者性の欠如、社員の個人情報の取り扱いへの不安も影響します。
以下は当社調査による退職面談(エグジットインタビュー)実施率と、本音で話せない率を対比したグラフです。
グラフを見ると、「上司との面談」では実施率59%と高い一方で、41%が「本音で話せない」と回答しています。唯一、実施率が「本音で話せない率」を上回る接点ですが、4割超が抑制されています。
ついで「人事との面談」でも同様に実施率29%に対し39%が本音を話せないと回答しています。さらに「社長との面談」では実施率が14%と低い一方で、本音で話せない率は46%と非常に高い結果となっています。退職アンケートや同僚との面談においても、本音を話せない割合が実施率を大きく上回っています。
インタビュー実施率/ホンネで話せない率
上司との面談
人事との面談
社長との面談
退職アンケートへの回答
同僚との面談
あてはまるものはない
多くの企業においてエグジットインタビューが導入されていますが、退職者が必ずしも本音を語るとは限らず、離職の根本的な原因を正確に把握することが難しい状況です。特にハラスメントなどの深刻な問題については、会社側に伝えられることなく退職に至るケースが少なくないと言われています。
このような「本音と建前」の壁を乗り越えるため、近年では心理師などの第三者がアバターなどの技術を活用して面談を行い、心理的安全性を確保した上で退職者の本音を引き出す専門サービスが登場しています。
よくある本音と建前の例
ここからは、退職面談や面接の場でよく聞かれる建前として挙がる「キャリアアップ」「家庭の事情」「給与への不満」を例に、その裏にある本音を紹介します。
「キャリアアップ」の裏側
建前:「スキルを高めるため」「新しい環境で挑戦したい」
本音:「現職での成長機会不足」「評価制度の不透明さ」「役割・裁量のミスマッチ」「スキルを高めたい」「新しい環境で挑戦したい」一見すると前向きな理由に聞こえますが、その裏には別の事情が隠れていることがあります。たとえば、現職で成長のチャンスが見えず、社員が会社の将来や自身の成長に不安を抱く状況があります。「やりたい仕事に手を挙げても声がかからない」「昇進の基準が分からない」そんな状況では、将来に不安を感じるのも無理はありません。
会社の評価制度への不信感もよくある話です。努力がどう評価されるのか分からない、上司によって基準が違う。こうした不透明さは、やる気を削いでしまいます。さらに、役割や裁量のミスマッチ。「期待される役割が曖昧」「意思決定権がなく、提案が通らない」。こうした不満が積み重なって、転職を考える人は少なくありません。
「家庭の事情」の裏側
建前:「育児や介護のため」「配偶者の転勤で」
本音:「柔軟な働き方の欠如」「長時間労働や突発対応」「両立支援の不備」
「育児や介護のため」「配偶者の転勤で」。退職理由としてよく聞く言葉ですが、社員が離職を選ぶ背景には別の事情があることがあります。たとえば、柔軟な働き方ができないこと。制度はあっても、実際には「在宅勤務は一部の職種だけ」「時短勤務はキャリアに不利」といった運用上の壁があります。
長時間労働や突発対応も大きな負担です。「シフトの融通がきかない」「閉店後の残務が当たり前」「製造ラインの都合で休みが取れない」。こうした現場の制約が、家庭との両立を難しくしています。さらに、両立支援の不備。育児や介護休暇の取得率は高くても、復帰後のフォローやキャリア形成のサポートが弱ければ、結局は離職につながる可能性があります。
「給与への不満」の裏側
建前:「給与に不満がある」「もっと稼ぎたい」
本音:「評価と報酬の連動不足」「市場水準との乖離」「昇給ルールの不明瞭さ」
「給与に不満がある」「もっと稼ぎたい」。退職理由としてよく挙がる言葉ですが、実際にはもう少し複雑な背景があります。大きいのは、評価と報酬のつながりが見えないこと。「成果を出しても昇給がない」「評価の理由が説明されない」。こうした不透明さは、納得感を損なう要因となります。
市場水準とのギャップも無視できません。同業他社と比べて「うちは低い」と感じると、転職意向は高まります。さらに、昇給ルールの不明瞭さ。「昇給のタイミングや基準がブラックボックス」という声は、特に若手からよく聞きます。
その他の例
「職場の人間関係」「経営方針の不一致」なども、退職理由としてよく挙がります。ただ、ここにも建前と本音のギャップがあります。たとえば、人間関係が原因の場合、表向きには「円満退職」と説明されることが多いものの、実際には特定の上司との意見の食い違いや、部署間のコミュニケーション不足が背景にあることが少なくありません。
また、会社の経営方針に納得できない場合も、「キャリアの方向性を見直したい」といった言い方をされることが多いですが、実際には会社の将来性への不安や、トップの意思決定に対する違和感などが理由になっているケースもあります。
本音を引き出す方法
退職理由の本音を聞き出すには、心理的安全性を確保し、信頼を築き、適切な質問を投げかけることが不可欠です。ここでは、面談を成功させるための3つの要素を解説します。
信頼を築く3つのコツ
1. 守秘と目的をはっきり伝える
面談の最初に「この内容は評価や再雇用に影響しません」「目的は組織改善であって、個人を責めるものではありません」と伝えましょう。これだけで、退職者は安心して話しやすくなります。
2. 傾聴と共感を大切にする
退職者が話し始めたら、最後まで遮らずに聞くことが大切です。相手の言葉を言い換えて確認しながら理解を示す「傾聴」により、安心感を与え、深い対話につながります。例えば「業務の進め方に不満がある」と言われたら、「具体的にどの点でしょうか?」と尋ねることで、話を具体化しやすくなります。
3. 感謝の意を具体的に表明する
これまでの会社への貢献に対し、抽象的な言葉ではなく「〇〇のプロジェクトでのご尽力には、チーム全員が本当に感謝しています」といった具体的なエピソードを交えて感謝を伝えることで、相手は一人の人間として尊重されていると感じ、本音を話しやすくなります。
退職面談の質問例
退職面談で本音を引き出すには、質問の仕方がとても大切です。ポイントは、オープンな質問と時系列の流れ(過去→現在→未来)。こうすることで、退職者が自分の経験を振り返りやすくなり、具体的なエピソードを語ってくれます。
以下に、実務で使える質問例とその狙いを挙げてみました。
1. 導入と関係構築(過去)
まずは退職者の経験を振り返ってもらい、話しやすい雰囲気を作ります。
| 質問 | 狙い |
|---|---|
| 入社前に期待していたことと、実際に働いてみて感じたギャップはありましたか? | ・採用活動やオンボーディングの課題を把握する ・候補者に誤解を与えていないか、入社後のサポート体制は十分かを確認する |
| この会社で働いていて、最もやりがいを感じた瞬間や、楽しかった仕事は何でしたか? | ・会社の「強み」や評価されている文化を特定する ・何が従業員のモチベーションに繋がっているのかを把握し、その要素を維持・強化するヒントを得る |
2. 退職理由の深掘り(現在)
退職の意思決定に関わる核心部分を、多角的な質問で深掘りします。
| 質問 | 狙い |
|---|---|
| 退職を決意するに至った、決定的な出来事やきっかけがあれば教えていただけますか? | ・退職の直接的なトリガーを特定する ・具体的なエピソードから、見過ごされていた問題や緊急性の高い課題を発見する |
| 仕事をする上で、一番エネルギーを消耗した、あるいは「きつい」と感じたのはどのような時でしたか? | ・業務負荷、業務設計、あるいは特定の人間関係における課題を明らかにする ・バーンアウト(燃え尽き症候群)の兆候や、非効率なプロセスがないかを探る |
| ご自身の仕事に対する評価や昇進・昇給について、どの程度納得していましたか? | ・評価制度の公平性、透明性、説明責任に関する課題を把握する ・従業員が正当に評価されていると感じられているかを確認する |
| 上司やチームメンバーとの関係性で、もっとこうだったら良かったと感じる点はありますか? | ・マネジメントの質やチーム内のコミュニケーションに関する具体的な改善点を抽出する ・1on1の機能性や、チームビルディングのあり方を見直すきっかけにする |
3. 未来に向けた提言(未来)
退職者の視点を「未来へのアドバイス」として活かします。
| 質問 | 狙い |
|---|---|
| どのような条件や環境が整っていれば、この会社で働き続ける可能性がありましたか? | ・リテンション(人材定着)施策の具体的なアイデアを得る ・退職を未然に防ぐために、会社が何をすべきだったのかを直接的に探る |
| これから入社される新しい職場に、最も期待していることは何ですか? | ・自社に欠けている魅力を逆説的に明らかにする ・市場における自社の競争優位性や、改善すべき福利厚生・キャリアパスなどを把握する |
| もしあなたが私の立場だったら、この組織を良くするために、まず何から始めますか? | ・当事者意識を持った、客観的かつ建設的な改善提案を引き出す ・「内部の人間だからこそ見える課題」に対する具体的なアクションプランのヒントを得る |
| 後任者やチームのメンバーに、何か伝えておきたいアドバイスはありますか? | ・スムーズな業務移行と、残るメンバーの働きやすさ向上に繋がるヒントを得る ・属人化している業務や、チーム内の暗黙のルールなどを可視化する |
避けるべき質問
退職面談で本音を引き出すためには、「聞いてはいけない質問」を避けることも大切です。間違った質問は、退職者を萎縮させ、防衛的にしてしまいます。
避けるべき質問の例
- 詰問調:「本当に家庭の事情ですか?」
- 責任追及:「誰のせいで辞めるんですか?」
- 引き留め前提:「給与を上げたら残りますか?」
- 守秘を曖昧にする:「この内容は必要に応じて共有します」
- 人名特定:「問題のある上司は誰ですか?」
こうした質問は、退職者にプレッシャーを与え、本音を隠させる原因となる可能性があります。代わりに、「どんな状況が働きづらさを生んでいましたか?」のように、人ではなく状況や仕組みに焦点を当てた質問に言い換えましょう。
また、個人情報や匿名性の担保は必須です。個人情報保護法や関連ガイドラインに沿った運用を徹底し、退職者が安心して話せる環境を整えることが前提になります。
本音を聞く仕組みづくり
退職理由の本音を安定して集めるには、個人のスキルに頼らない仕組みが必要です。「聞き上手」な担当者に任せるやり方では、再現性も信頼性も確保できません。
ポイントは、第三者による面談、匿名性の担保、そしてデータの一元管理。この3つを組み合わせることで、属人的な判断に左右されず、継続的に本音を収集できる仕組みを構築できます。
単発の面談で終わらせず、仕組みとして運用することが重要です。そうすることで、企業は退職理由を正確に把握し、根本的な課題を抽出し、改善策を実行するための基盤を整えることができます。
第三者面談の活用
退職者が本音を語れない最大の理由は、利害関係のある相手に話す不安です。直属の上司や社内人事が退職面談を担当すると、「評価や推薦に影響するのでは」という懸念から、率直な意見を避ける傾向があります。
そこで有効なのが、第三者による面談です。外部の専門家や、評価権限を持たない別部門の担当者が対応することで、心理的安全性は大きく高まります。さらに、オンライン面談やアバターの活用も効果的です。顔出し不要の形式は、プライバシーへの配慮と心理的負担の軽減につながると考えられます。
第三者面談を成功させるポイント
- 面談の目的と守秘範囲を冒頭で明確に伝える
- 評価や再雇用に影響しないことを保証する
- 面談者は傾聴スキルを持つ専門家(心理師など)を起用する
外部の専門家が関わることで、中立性が保たれ、退職者は安心して本音を話せます。また、オンラインやアバターを使えば、顔出しのプレッシャーを減らし、より率直な意見を引き出せます。さらに、定期的に第三者面談を実施すれば、退職理由の変化や組織課題の傾向を継続的に把握でき、改善策の精度も高まります。
匿名性を担保する方法
本音を引き出すためには、個人情報保護法に準拠した匿名性の確保が重要です。発言者が特定されないよう、収集した情報は「仮名加工」や「匿名加工」といった法的に定められた手法で適切に処理する必要があります 。
守るべきポイント
- 目的を説明し同意を得る: 「組織改善のため」など目的を限定し、「個人評価には使わない」ことを明確に伝えます 。
- 個人情報を分離・加工する: 氏名や社員番号などを削除し、個人を特定できない統計データとして扱います。
- 安全に管理する: データは暗号化し、アクセス権限を最小限に絞るなど、厳格な管理を行います。
避けるべきNG例
- 面談記録を個人が特定できるまま部署に共有する。
- 属性情報(部署や役職など)から個人が推測できる状態でレポートを作成する。
-
同意なく情報を目的外に利用したり、無期限に保管したりする。
これらのルールを徹底することで、退職者は安心して本音を話すことができ、企業は法的なリスクを回避しながら、価値ある情報を得ることができます。
個人情報保護委員会「匿名加工情報と仮名加工情報の違いは何ですか」
面談とサーベイの連携
最も効果的な仕組みは、定性データと定量データを組み合わせるアプローチです。インタビュー(定性)で個別の深い本音を掘り下げ、サーベイ(定量)で組織全体の傾向や課題の優先順位を客観的に把握する。この両輪が、精度の高い課題特定に繋がります。
当社のサービス「退職のホンネ」も、このインタビューとサーベイを掛け合わせることで、数値の背景にあるリアルな声を深掘りし、課題の真因を多角的に可視化する強みを持っています。
関連サービス:退職のホンネ|本音を探る退職面談サービス|離職防止と組織改革へ |パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
本音データの活用と改善策
退職面談やサーベイで集めたデータは、集めただけでは意味がありません。大切なのは、そこから原因を見つけ、見える化し、改善につなげることです。本音データは、個々の声で終わらせず、統計的に分析して真因を明らかにすることで、組織改善の強力な材料になります。
このデータをもとに、改善策を立て、実行し、効果を検証する。PDCAを回すことで、離職率の低下やエンゲージメント向上、採用コスト削減といった具体的な成果につながります。
真因分析のポイント
退職理由をそのまま信じても、改善は進みません。必要なのは、表面的な言葉を整理し、因果関係を見極めることです。
まず、自由記述や面談記録を「評価」「上司」「制度」「働き方」などのカテゴリに分類します。次に、どの要因が一緒に出てくるかを分析し、因果関係の仮説を立てます。たとえば「評価制度の不透明さ」→「成長機会の欠如」→「キャリアアップ転職」といった流れです。最後に、部署や職種ごとに傾向を比較し、再現性を確認します。
分析では、サンプル数やバイアスに注意し、複数のデータソースで補完することが重要です。個人情報は必ず匿名化し、アクセス権も制限します。
本音データをこうして構造化・分析することで、単なるコメントでは見えない根本原因を特定できます。これが、組織改善を成功させる鍵です。
ダッシュボードでの可視化
分析結果は、経営や現場が一目で理解できる形にすることが大切です。そのために、ExcelやBIツールを使ってダッシュボードで可視化します。
表示するのは、退職理由のカテゴリ別割合や部署別の真因ランキング、感情スコアの推移、改善施策とKPIの連動状況など。時系列で変化を追える設計や、重大発言を示すヒートマップ、自由記述のキーワードクラウドを組み合わせると、現場感も共有できます。
ダッシュボードは、ヒートマップやグラフで直感的に把握できるようにします。さらに、面談の感情スコアを数値データと並べて表示すれば、数字の背景にあるリアルな声も見えます。改善策の効果を定期的に確認し、PDCAを回す仕組みとしても有効です。
導入のステップと注意点
退職理由の本音を可視化する仕組みを導入する際は、法令を守りながら、運用を安定させることが欠かせません。特に重要なのは、同意取得と情報管理の徹底、そして小規模なパイロット導入で仕組みを検証することです。
同意取得と情報管理
退職面談やサーベイで本音データを収集するには、同意取得と情報管理の徹底が不可欠です。
同意取得では、目的(例:「組織改善のため」「個人評価には使用しない」)、利用範囲、第三者提供の有無、保存期間、同意撤回の方法を明示し、文書やデジタル署名で確認します。情報管理では、氏名や社員番号を分析データから切り離し、匿名加工や仮名加工を適用します。アクセス権は最小限に制限し、ログを記録、データは暗号化して保存します。
NG例として、面談記録をそのまま部署に共有する、保存期間を定めず無期限保管する、目的外利用(評価や査定への転用)などがあります。これらを守ることで、退職者の信頼を確保し、安全にデータを活用することができます。
パイロット導入の流れ
全社展開の前に、限定的なパイロット導入を行うことで、リスクを抑えつつ効果を検証できます。
まず、対象部署を選定します(離職率が高い部門や改善意欲のある部門)。次に、期間を設定し(例:四半期)、第三者面談とサーベイを実施します。評価指標は、面談・サーベイ実施率、本音検出率、改善アクション件数、KPI(離職率やエンゲージメントスコア)との連動状況などです。
結果をレビューし、運用ルールを見直したうえで、Go/No-Goを判断し、必要に応じて全社展開に移行します。経営層にはダッシュボードやレポートで報告し、現場には迅速にフィードバックを行うことが重要です。
まとめ:本音を可視化する重要性
退職は、企業にとって避けられない出来事ですが、それは単なる人材流出という「損失」ではありません。退職者が最後に残してくれる「本音」は、組織の隠れた課題を映し出し、未来の成長につながる貴重な経営資源です。
退職者の本音を可視化し、データに基づいた組織改善サイクルを回していくこと。それが、これからの人的資本経営において不可欠な一手となるでしょう。しかし、その仕組みをゼロから構築するには、専門知識やリソースが必要です。
本音を引き出す退職面談サービス、「退職のホンネ」
パーソルビジネスプロセスデザインでは、退職予定者の本音を探る「退職のホンネ」をご提供しています。心理師による第三者面談とサーベイを組み合わせ、退職理由を定性・定量の両面から分析し、組織課題の可視化を実現します。
- 傾聴に長けたプロの心理師が対応(臨床心理士/公認心理師資格保持者)
- アバターを活用したオンライン面談
- インタビューとサーベイを掛け合わせ、“ホンネ”をデータ化、組織課題の可視化を実
すぐにダウンロード可能なサービス概要資料をご用意しておりますので、本音を可視化する仕組みづくりの第一歩をご確認ください。