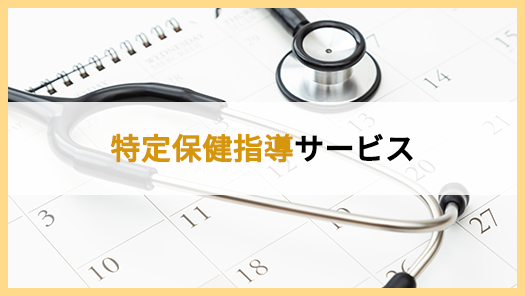今さら聞けない「特定保健指導の動機づけ支援」とは?
動機づけ支援とは、対象者が自ら生活習慣を改善する「やる気」を引き出し、行動変容の第一歩を後押しするための、極めて重要なプログラムです。
単なる知識の提供ではなく、対象者の内発的動機を高め、継続可能な生活習慣の変化を促進することが目的となります。
動機づけ支援の目的と対象者
動機づけ支援の目的は「行動変容のきっかけ作り」であり、対象者はメタボリックシンドロームのリスクが出始めた段階の人になります。
具体的な選定基準として、腹囲(男性85cm以上、女性90cm以上)またはBMI25以上に加え、血糖・血圧・脂質の検査値や質問票の回答結果に基づいて対象者が決定されます。
重要なポイントは、重症化する前の段階、つまり本人の危機感がまだ低い時期に介入することです。自覚症状がない段階での取り組みとなるため、対象者に「自分事」として捉えてもらうことの重要性と難しさを理解しておく必要があるでしょう。
なぜ今、動機づけ支援の質が重要視されるのか?
では、なぜ今「動機づけ支援の質」が重要視されているのでしょうか?
それは、国民医療費の増大や、企業の「健康経営」への関心の高まりという社会的な背景があります。
健康保険組合連合会の調査(令和3年度)によると、健保組合の総医療費のうち生活習慣関連10疾患の医療費は約12.6%を占めています。こうした状況を踏まえ、国の医療費抑制というマクロ視点と、企業の生産性向上や人的資本経営といったミクロ視点の両面から、一人ひとりの動機づけ支援の重要性が改めて認識されています。
さらに、体調不良による生産性低下(プレゼンティーイズム)の改善効果も期待されており、投資対効果の明確化が求められています。
※参考:令和元年度 生活習慣関連疾患医療費に関する調査
※参考:健康経営への取り組みに対する企業の意識調査|株式会社 帝国データバンク[TDB]
「動機づけ支援」と「積極的支援」との違い
次に積極的支援との違いについて解説していきます。
一番の違いは、介入期間の長さと支援の密度が大きく異なる点です。動機づけ支援は、原則1回の支援を行い、3か月以上経過後に評価を行うのに対し、積極的支援は3か月以上の長期間にわたって「習慣化サポート」を提供します。
また、動機づけ支援では初回面談のみで対象者の動機を引き出すことが中心となりますが、積極的支援では複数回の継続的な面談や支援を通じて生活習慣の定着を図ります。対象者のリスク度についても、動機づけ支援は中リスク、積極的支援は高リスクと区分され、それぞれ異なるアプローチが求められるのが特徴です。
動機づけ支援では短期間でいかに効果的に動機を引き出すかが成功の鍵となり、積極的支援では長期間のモチベーション維持と行動継続が重要になる点が異なっているといえるでしょう。
特定保健指導の担当者が直面する"3つの壁"
特定保健指導がうまくいかない真の原因は、対象者個人の問題だけでなく、担当者が必ず直面する3つの構造的な課題(3つの壁)にあります。
- 実施率の壁
- 継続率の壁
- 体制の壁
多くの担当者が感じている「うまくいかないもどかしさ」は、実は個人の能力不足ではなく、制度設計や運用体制に起因する共通の課題なのです。それでは、一つずつ解説していきます。
実施率の壁・・・そもそも受診勧奨に応じてもらえない
一つ目の壁は、「実施率」です。
対象者の多くは「自分はまだ大丈夫」「忙しくて面倒」と感じており、一方的な案内だけでは参加につながりにくいのが現状です。健康診断の結果を見ても「去年とほぼ変わらない」「この程度なら問題ない」と捉えている方が多く、緊急性を感じていないケースも少なくありません。
また、被保険者は職場での一斉案内や上司からの推奨、健診や面談といった複数の参加促進の接点を持ちますが、被扶養者は自宅への郵送物やウェブサイトの案内など、より受動的で限定的な情報提供に頼らざるを得ません。そのため、参加してもらうこと自体、一枚岩ではありません。被保険者にとっては比較的低い壁である一方、被扶養者の参加を促すことが非常に高い壁といえるでしょう。
令和5年度の全国健康保険協会連合会(健保連)の調査では、被扶養者の特定保健指導実施率は被保険者の約半分にとどまっており、構造的な課題として多くの保険者が頭を悩ませています。
こうした背景を踏まえ、対象者の立場に寄り添った参加しやすい環境づくりと、心に響くメッセージの工夫が欠かせません。
※参考:令和5年度 特定健診・特定保健指導の実施状況(速報版)
継続率の壁・・・対象者のモチベーションが続かず、途中で離脱してしまう
二つ目の壁は「継続率」です。
生活習慣の改善は孤独な戦いであり、初期のやる気や危機感だけでは3か月間モチベーションを維持することは困難です。特に動機づけ支援は初回面談後のフォローが限定的なため、対象者の孤立感が高まりやすい傾向があります。
モチベーションが低下する場面としては、成果がすぐに見えないことへの焦りが最も多く見られます。また、家族や職場の協力が得られない孤独感、定期的なフィードバックがないことによる不安、日常業務の忙しさによる優先順位の低下なども要因として挙げられるでしょう。
継続的なエンゲージメントを維持する仕組みづくりが重要になります。
体制の壁・・・他業務との兼任で、十分なリソースを割けない
最後の壁は「体制」です。
これは、担当者の熱意や努力だけでは乗り越えることができない時間的/人的リソースの限界という現実的な問題を指します。
健康保険組合の本来の業務(コア業務)として、保険証の発行、保険料の支払い手続き、健康診断の予約を企業から請け負うなど、定常的に行う必要がある業務があります。
それに加えて、特定保健指導に関連する付帯業務の負担も深刻です。具体的には、対象者のリストアップから始まり、案内状の作成・送付、日程調整、未実施者への再勧奨、データ入力・集計、効果測定、報告書作成まで、膨大な事務作業が発生します。
本来の組合業務と並行してこれらを実施することの負担感は、担当者の継続的なモチベーション維持を困難にしているでしょう。このように組織体制の見直しが必要になる点も課題(壁)として挙げられます。
動機づけ支援を成功に導く、3つの実践ポイント
動機づけ支援を行う上で、前述した課題(壁)がありますが、以下のポイントを抑えることで、動機づけ支援を成功に近づけることができるでしょう。
- 対象者の「変わりたい」気持ちを引き出す対話術
- ICTツールも活用し、参加・継続のハードルを下げる
- 小さな成功体験を可視化し、行動変容を促す
これらの「対話」「環境」「可視化」の3つを工夫することで、対象者の「やらされ感」を「やる気」に変え、自発的な行動変容を後押しすることができます。理論的な背景だけでなく、実際の現場で活用できる具体的なテクニックを中心に解説します。
ポイント(1)対象者の「変わりたい」気持ちを引き出す対話術
まずは、一方的に指導するのではなく「対話」を通じて対象者の中から答えを引き出す「動機付け面接」のアプローチが有効となります。相手の自律性を尊重し、変化への内発的動機を高めることで、持続的な行動変容につながるでしょう。
実際のコミュニケーション例としては、「運動をするべき」と一方的に伝えるのではなく、「運動したい気持ちと、したくない気持ち、両方ありますよね」と矛盾する感情に寄り添う表現を用いることが効果的です。
また、「もし変化するとしたら、どんな小さなことから始められそうですか?」といったオープンな質問を通じて、対象者自身に目標を立ててもらうことが重要です。
ただし、実際にこのアプローチを組織的に導入・活用するには、いくつか注意すべき点があります。
例えば、「指導者間でのスキル格差」や「面談品質のばらつき」などは、指導の効果に直結するため特に注意が必要でしょう。そのため、専門的な研修の実施、面談内容の定期的なレビュー、標準化された面談プロトコルの整備など、品質を担保する仕組みづくりが不可欠となります。
ポイント(2)ICTツールも活用し、参加・継続のハードルを下げる
オンライン面談やスマートフォンアプリなどのICTツールを活用も成功には不可欠な要素となります。
特にコロナ禍以降、非対面での健康支援に対する受容性が高まっており、ICT活用の効果が期待されています。実際に、対象者の時間的・場所的な制約を取り払うことで、参加・継続のハードルを心理的にも物理的にも下げることできるでしょう。
具体的なツールとしては、好きな時間に予約できるオンライン予約システム、スマートフォンで食事や歩数を簡単に記録できるアプリ、ウェアラブルデバイスとの連携による自動データ収集、チャットボットによる24時間対応の相談窓口などが挙げられます。これらは、対象者の「面倒くさい」「忙しい」といった心理的なハードルを下げ、継続しやすい環境を整備する上で有効です。
一方で、ICT活用には注意も必要です。
デジタル機器の操作に不慣れな方や高齢の対象者にとっては、逆に参加の障壁となる可能性も指摘されています。また、「アプリの使い方が難しい」「登録手続きが複雑で手間」といった理由で離脱するケースもあります。
そのため、ICTツールの導入時には、個人のリテラシーに合わせた丁寧なサポートを提供するとともに、対面・オンライン・アプリなど複数の選択肢を用意し、対象者が自分に合った方法を選べる「ハイブリッド型」の支援体制を整えることが重要です。
ポイント(3)小さな成功体験を可視化し、行動変容を促す
動機づけ支援を成功させるためには「成功体験を可視化」させることが重要です。
体重の微減や行動の変化をグラフなどで「見える化」し、小さな成果を積極的に褒めることで、対象者の自己効力感を高めることができます。また結果だけでなく、プロセスそのものを評価することが継続的なモチベーション維持につながるでしょう。
例えば、「マイナス2kg」という数値的な結果だけでなく、「エレベーターを階段に変えた」「間食を減らせた日が週3回あった」といった行動の変化そのものを評価し、ポジティブなフィードバックを与えることが重要です。
小さな変化でも「確実に前進している」という実感を対象者が持つことで、次の行動への動機が生まれ、自然な習慣化につながるでしょう。
専門性・リソース不足を解消する「外部委託」という選択肢
動機づけ支援を成功に導くポイントを解説しましたが、実践していくにあたり「専門性」「リソース」に関して課題を感じる場面も出てくるはずです。
そのような時には、専門知識とリソースを持つ外部パートナーの活用が最も有効な選択肢の一つとなるでしょう。内製での取り組みに限界を感じた際には、より戦略的なアプローチで事業成果の向上を目指すことが求められます。
外部委託で得られる3つのメリット
専門知識とリソースを持つ外部パートナーへ、業務の一部または全部を委託することのメリットは主に次の3点が挙げられます。
- 質の高い支援による、成果の向上
- 業務負荷を軽減でき、コア業務へのリソースを捻出
- マンネリ化している指導方法の刷新
特定保健指導を熟知した外部パートナーであれば、認知行動療法やコーチング技術を活用した科学的根拠のあるプログラムにより、従来の画一的な指導から脱却し、個別性を重視した支援が可能になるでしょう。
また、保健指導に関する一連の業務をアウトソーシングすることで、工数を削減できるだけでなく、空いたリソースでより戦略的な業務に集中できるようになります。具体的には、対象者のリストアップから結果集計までを包括的に依頼することで、担当者はコア業務に専念できる環境が整います。
内製による保健指導を継続しているなかで、指導方法のマンネリ化を課題に感じる担当者も多いのではないでしょうか。外部パートナーへ委託することで、最新のノウハウやツールを活用でき、マンネリ化した従来の指導方法を刷新できる効果も期待できるでしょう。
これらの相乗効果により、組織全体の健康経営推進にも寄与します。
失敗しないための外部ベンダーの選び方
外部委託のベンダーを選定する際には、以下の5つの観点で総合的に評価することが重要です。単に価格のみを比較するだけでなく、組織の課題解決に最適な価値を発揮することができるパートナーを見極めましょう。
- 過去の支援実績
- プログラム内容(支援方法)
- サポート体制
- 柔軟性
- 費用
実績については、「指導実績人数」「実施率」「継続率」などの具体的な数値データを確認しておきましょう。特に、同業界、同規模の健康保険組合を支援してきた実績があるかどうかは重要な判断材料になります。
プログラム内容では、指導者の資格・経験、面接技法の種類、教材の質、科学的根拠の有無を詳細に確認する必要があります。具体的な支援方法やそのフローをもれなく確認しておくことで、対象者にとって適切なアプローチとなるかどうかの判断ができるでしょう。
サポート体制面の評価も重要です。実施前の準備支援から実施中のフォロー体制、報告業務の支援範囲、トラブル対応まで、包括的な支援が受けられるかを確認しましょう。
柔軟性については、面談方法の選択肢(対面・オンライン・電話)、実施時間帯の調整可能性、カスタマイズ対応の有無を確認しましょう。実施率が改善しない場合など、原因を見つけリカバリーに取り組んでもらうことができる柔軟性を評価しておくことが重要です。
費用面では、初期費用・運用費用の内訳、追加オプションの料金体系、費用対効果の明確性を総合的に判断することが求められるでしょう。単に安価なパートナーを選定した結果、「見込んでいた成果が出ない」などの状況を避けることが重要です。
パーソルビジネスプロセスデザインの特定保健指導サービス
パーソルビジネスプロセスデザインでは、健康保険組合が抱える特定保健指導の実施率や継続率の課題に対し、9万人超の対応実績に基づいた独自のノウハウと、認知行動療法に基づく科学的アプローチを活用したサービスを提供しています。
さらに、単なる業務代行にとどまらず、健保担当者の事業企画力向上支援や運営パートナーとしての伴走支援も重視。対象者への勧奨から実施、報告までをワンストップで支援することで、現場の負担を大きく軽減しながら、成果につながる保健指導を実現します。
※関連サービス:特定保健指導サービス
「動機づけ支援」の質を高め、保健指導の成果を最大化しよう
動機づけ支援の成功は、対象者の健康改善だけでなく、担当者の業務負担軽減や組織全体の健康経営推進にも繋がる、価値ある取り組みです。実施率・継続率の向上という数値的な成果はもちろん、加入者の健康意識向上や医療費適正化といった中長期的な効果も期待できます。
本記事で紹介した「対話術」「ICT活用」「可視化」の3つの実践ポイントを明日から取り入れることで、現在のマンネリ化した状況を打破し、対象者の行動変容を促進できるでしょう。同時に、自組合のリソースや専門性を客観的に評価し、必要に応じて外部委託の活用も検討することで、より効率的で効果的な事業運営が実現できます。
「今年こそは変化を起こしたい」という想いを具体的な行動に移し、加入者の健康と組織の成果の両方を向上させる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。専門的な支援が必要な場合は、実績豊富なパートナーとの協力により、確実な成果創出を目指すことが重要です。