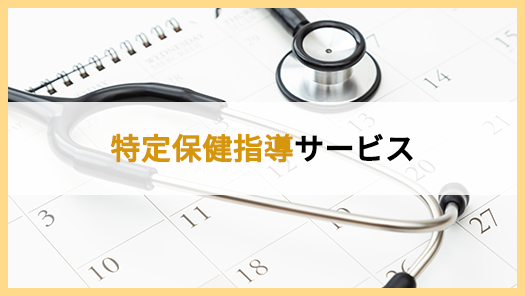特定健診・特定保健指導とは?
特定健診とは、生活習慣病の予防を目的に、対象者(40歳~74歳)に向けて実施される「特定健康診査」を指します。メタボリックシンドロームに着目した健診となるため、一般的に「メタボ健診」と呼ばれています。
また、特定健診において生活習慣病のリスクが発見された方を対象に実施する保健指導を「特定保健指導」と言います。
特定保健指導では、医師や保健師、管理栄養士をはじめとした専門家のアドバイスを受けることができます。また、検査結果・症状に応じて一人ひとりに合わせた生活習慣を見直す支援を行われることから、意欲的な参加が効果的と言えるでしょう。
厚生労働省の報告によると、2023年度の特定健診の実施率は59.9%、特定保健指導の実施率は27.6%となっています。この数値は2008年度以降で最も高い数値となっていることから、特定健診・特定保健指導への意識が高まっていると言えます。
自覚症状が出にくい生活習慣病によるリスクを早期に発見し治療していくためにも、健康な状態での受診が必要となるため、定期的な受診を促しましょう。
※参考:厚生労働省「2023年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(概要)」(PDF)
特定健診・特定保健指導の基本的な流れ
特定健診・特定保健指導の基本的な流れとしては、まず特定健診を受診して腹囲や体重、血糖値、血圧、脂質などを検査します。
そこで基準値内であった場合には「特段対応なし」となり、指導を受ける必要はありません。ただ、病気の判定まではいかないけれども正常値よりも高い項目があり、生活習慣の改善が必要であると判断された場合には、特定保健指導の対象となります。
特定保健指導では、食生活や運動習慣の見直しといった生活習慣の改善支援が行われます。また、健診結果に問題があり、精密検査や病気の治療等が必要であると判断された場合には、当然ながら医療機関への受診が必要になります。
特定健康診査の検査項目
特定健診では、以下の項目が検査対象となります。
| 分類 | 検査項目 |
|---|---|
| 基本的な健診の項目 | 質問票(服薬歴、喫煙歴等) |
| 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) | |
| 理学的検査(身体診察) | |
| 血圧測定 | |
| 血液検査 | |
| 脂質検査(空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪(空腹時(絶食10時間以上)以外に採血を行う。))、HDLコレステロール、LDLコレステロール) | |
| 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合には随時血糖) | |
| 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)) | |
| 検尿(尿糖、尿蛋白) | |
| 詳細な健診の項目 | 心電図検査 |
| 眼底検査 | |
| 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値) | |
| 血清クレアチニン検査 ※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施 |
特定保健指導を受けることによる効果は?
特定保健指導を受けることで得られるメリットは多く存在しますが、特に大きなメリットとしては「メタボ・肥満の改善が期待できること」が挙げられます。
2008年に国立循環器病研究センターは、特定健診を受診してメタボリックシンドロームと診断された約2,000万人を対象に調査を行いました。
その結果、特定保健指導を受診した人たちは、受診しなかった人たちに比べ、3年後に再度メタボリックシンドロームと診断される割合が31%も減少したといいます。
国家レベルの政策である特定健診・特定保健指導が個人の生活習慣改善に大きなメリットがあることがお分かりいただけると思います。
特定健診・特定保健指導を受けないとどうなるのか?
特定健診・特定保健指導は法律で定められた制度であり、医療保険事業を運営する医療保険者は実施が義務づけられています。
もし実施率が低い場合には、ペナルティーとして保険者が国に納める後期高齢者支援金が加算されてしまうのです。また、加入者自身が特定健診を受診しなければ、当然ながら「生活習慣病予防のチャンス」を失うことになり、生活習慣病の発生リスクを高めてしまいます。
そもそも特定健診は40歳から74歳までが対象となりますので、20代や30代の時よりさらに健康に気を配る必要性があります。
その中でも特定保健指導の対象者になるということは、年齢以外の要因でも生活習慣病の発症リスクがあるということです。特定健診で保健指導の対象となった方はしっかりと指導を受けるようにしましょう。
特定健診・特定保健指導を受けないと企業側のリスクは?
社員のパフォーマンス向上や業務の生産性向上を目指すのであれば、社員の心と体の健康が欠かせません。
近年、「社員の健康」を経営的な課題ととらえ、「健康経営」を推進することが重要視されています。企業に実施義務があるのは労働安全衛生法で定められた「健康診断」であり、特定健診の実施義務はありません。
ただし、企業と医療保険者の連携すること(コラボヘルス)には、健康課題の特定や健康施策の共有などにおいて効率的に行えるというメリットがあります。
また、社員が特定保健指導を受けることにより、生活習慣の改善に取り組むメリットを実感できれば、自分自身の健康に対する意識も向上していくでしょう。
そのような形で社内全体の健康意識が向上していけば、長期的には、緊急入院や長期療養などで社内の戦力が著しく低下するといったリスクを回避することができます。
特定保健指導の実施率向上を目指すならパーソルビジネスプロセスデザインへ
特定健診・特定保健指導が企業にとって非常に重要なものであることがお分かりいただけたでしょうか。
パーソルビジネスプロセスデザインの「特定保健指導支援サービス」では、第4期特定保健指導「アウトカム評価」にこだわり、管理栄養士・健康運動指導士・心理師の専門的な指導が受けられます。
心理学的アプローチで、体重を減量させる取り組みと減量した体重を維持するスキルの獲得を促すプログラムです。きめ細かいフォローによって継続率は97.2%(2024年度実績)と高く、多くの健康保険組合様から高い評価をいただいています。
ご質問などあれば、ぜひお気軽にパーソルビジネスプロセスデザインまでお問い合わせください。